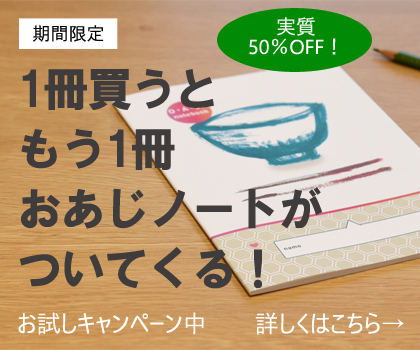味わいも大事、でも日持ちも大事。ここが腕の見せドコロ
牛乳の加熱殺菌は味わいを決める繊細な工程
牛乳は牧場で搾ってから皆さんの食卓に届き消費するまでに一定の時間が必要なため、日持ちさせるために加熱殺菌が行われています。日本酒に火入れをするのも、発酵を止めて劣化を防ぐためのものと言われていて、こうした発酵や熟成では温度管理が重要なポイント。牛乳の加熱殺菌もまた、温度や手法によって風味や色、味わいなどを左右する繊細な工程です。
殺菌のバリエーションは「時間」と「温度」
大きくは「高温で短時間」か「低温でじっくり」に分かれますが、日本の乳業メーカーのほとんどは「高温で短時間」の手法を選択しています。
「低温でじっくり」の歴史は長く、フランスの科学者で、免疫学をはじめ生物学・細菌学・医学・農学まで幅広い専門を持つルイ・パスツールが腐敗を防ぐために開発したのが始まりです。彼の名前を冠して、低温殺菌のことをパスツリゼーションと呼んでいます。
乳業メーカーのこだわりと差別化に
パスツリゼーションとは、液体を60℃程度で数十分加熱することで細菌などの微生物を殺菌するもので、牛乳では“パスチャライズ製法”や“パスチャライズド乳”などと呼ばれて普及しています。しかし高温でガツンと瞬間殺菌をするよりも、低温な分だけその工程や搾乳からの手間もかかるため、日本では少量生産になっていましたが、近年では流通での温度管理体制も整っており「65℃で30分間」「80℃で15分間」などメーカーの工夫が広がってきています。